はじめに:なぜ「太陽光×EV」が注目されているのか
脱炭素社会に向けた流れ
近年、脱炭素社会の実現に向けた動きが世界中で加速しています。
日本も、2050年までにカーボンニュートラルを目指すことを宣言しており、再生可能エネルギーの推進や炭素税、排出量取引制度の導入を検討するなど脱炭素の動きが活発化しています。
EVは走行時にCO2を排出しないため、太陽光発電などの再生可能エネルギーで充電することで脱炭素社会の実現に寄与することができます。
電気代高騰の影響
世界的なエネルギー需給の逼迫や地政学的リスクにより化石燃料の価格が高騰しています。
これに伴い電気料金も上昇傾向にあります。
太陽光発電で自家発電した電力をEVの充電に理由することで、電力会社からの購入電力を減らすことができます。
これにより、電気代の高騰リスクを軽減することができます。
災害時の対策
EVは大容量のバッテリーを搭載しておりV2H技術を利用すれば災害時でも家庭用電源として活用できます。太陽光と組み合わせることで、停電時でも電力を供給することができます。
EVと太陽光発電の相性
EVと太陽光の組み合わせは、環境貢献、経済的メリット、災害対策など多くの面で相性が良いと言えます。
技術的にも社会的にもこの組み合わせは脱炭素社会に向けた重要なソリューションとして注目されており、今後さらに普及が進むことが期待されています。
太陽光×EVの仕組みとは
太陽光発電の基本的な仕組み
太陽光発電では以下のような流れで発電し使われます。
- 太陽光パネルが太陽光を受けて直流(DC)の電気を発生
- パワーコンディショナー(パワコン)で家庭用の交流(AC)に変換
発電された電気の使い道は「自家消費」「売電」「蓄電」の3つあります。
「自家消費」とは発電した電気を家庭内の電力として直接使うことです。
「売電」とは、発電された電力のうち、余った電気を電力会社に売ることです。
「蓄電」とは、発電された電力を蓄電池に溜めることです。
かつては売電価格が1kWhあたり42円と高かったため余剰電力を売る方が主流でした。
現在では売電価格が十数円と安くなっています。
そのため、日中に「自家消費」+「蓄電」して、日没後は蓄電した電力を消費する、という運用方法が経済メリットを享受しやすいく、注目されています。
そして「蓄電」するためには蓄電池を購入し設置する必要があります。
EVの基本的な仕組み
EVは大容量のバッテリーを搭載しており、バッテリーに電気を「充電」することで走行することができます。
一般的な家庭用蓄電池の容量が〜20kwhなのに対し、EVのバッテリーの容量は〜100kWhあります。
この大容量のバッテリーを蓄電池として活用する方法があります。
それがV2Hです。
V2Hの役割と仕組み
V2H(Vehicle to Home)とは、電気自動車に搭載されたバッテリーを家庭用電源として活用する技術のことです。
V2Hによって、電気自動車を蓄電池として活用することができます。
太陽光×EVのメリット
電気代の節約
昼間に太陽光で発電した電力をEVに充電し、夜間にEVから家庭に放電することで、電気の購入量を抑え電気代を節約することができます。
非常用電源として活用
停電が起きた時もEVに充電した電力を家庭内で使うことができます。
太陽光発電だけだと晴れている昼間の停電にしか対応できませんが、EVから家庭に放電することで夜間の停電にも対応できます。
また、家庭用蓄電池では停電が長引いて、なおかつ悪天候が続くと晴れの日を待たなければなりませんが、EVは停電していない充電スポットまで運転して充電しに行けば、電気を運んでくることができます。
環境に優しいライフスタイル
EVは走行中には排気ガスを排出しませんが、充電した電気が必ずしもクリーンとは限りません。
太陽光発電の電気で充電すれば、より環境に優しいライフスタイルを実現することができます。
太陽光×EVのデメリット
初期費用が高い
太陽光×EVを組み合わせると導入コストがネックとなってきます。
主にかかる費用は以下
- 太陽光発電システム(5kw前後):約100〜150万円
- V2Hシステム:約100〜150万円
- EV本体:約300〜500万円
合計すると600〜800万円ほどかかるケースもあり、高額な初期投資となります。
移動中は蓄電できない
EVは自動車なのでもちろん移動手段としての側面があります。
平日の買い物や送り迎えはもちろん、週末のお出かけや旅行などで車で移動することがあります。家庭用蓄電池は常に自宅にあるのでお出かけ中も蓄電してくれますが、EVの場合は移動中は蓄電できません。
どんな人に太陽光×EVは向いているのか
電気代を節約したい人
電気代が年々上がっている今、電気を買うより作って使う方がコストを抑えられます。特にオール電化住宅では電気の使用量が多いため、太陽光発電でまかなうことで月々の電気代を削減することができます。
さらにEVがあれば、昼間に発電した電気をEVに充電し、夜にその電気を使うことで電気代の削減効果を最大化できます。
EVをすでに持っているorこれから買う予定の人
EVはガソリン代が不要で経済的なメリットがありますが、充電により電気代が増えるデメリットもあります。そこで太陽光発電と組み合わせることで燃料代ほぼゼロの運用が可能になります。
更にV2HがあればEVに充電した電気を家庭に供給できるため、EVを移動できる蓄電池として活用することができます。
災害・停電時の備えをしたい人
日本は台風・地震・豪雨など自然災害が多いため、停電のリスクが常にあります。太陽光発電があれば昼間は発電した電気を使えて、さらにEVや V2Hがあれば、夜も電気を確保できるため災害時の安心感が格段に上がります。
FIT期間が終わる、すでに終わった人
売電の固定価格買取制度(FIT)が終了すると売電価格が大幅に下がり、売るメリットより使うメリットの方が大きくなります。
そこでEVを活用すれば、昼間に充電したEVの電力をよる使うことができます。
終わった人だけではなく将来終わることを見据えて「使う」ライフスタイルを獲得していきたい方にも向いていると言えます。
環境意識が高く持続可能なエネルギーに興味がある人
太陽光発電とEVを組み合わせることで、100%再生可能エネルギーで車を動かすことができ、クリーンな移動手段を手に入れることができます。
環境意識が高く、脱炭素やゼロエミッションに興味がある人にとっては太陽光×EVは理想的な選択肢の一つとも言えます。
実際に導入する際のポイント
補助金・助成金の活用
太陽光×EVの導入を検討する際、国や自治体から提供される補助金や助成金を活用することで初期費用の負担を軽減することができます。
CEV補助金
EVやPHEVの普及を促進するため、充電インフラの整備を支援するもの。V2Hの導入に対しても補助が適用されます。
各自治体の補助金・助成金
各都道府県や市町村でも太陽光発電システムやV2Hの導入に対する独自の補助金や助成金を設けている場合があります。
補助金や助成金には、申請期間や予算の上限が設定されているため、早めに情報を収集し、計画的に準備をすることが重要です。
また、申請手続きや条件が複雑な場合には専門の業者やコンサルタントなどに相談することが望ましいでしょう。
V2Hの選び方のポイント
EVとの互換性
自身の所有しているEV、購入予定のEVに対応しているか、相性はどうかがまず重要なポイントとなります。
充放電の性能
省エネ目的や小規模な電力供給向けであれば標準タイプ(3〜6kw)で十分ですが、エアコンやIHなども使いたい方は高出力タイプ(6〜9.9kw)を選んだ方が良いでしょう。
停電時の対応
停電時に、自動でEVの電力を家庭に供給してくれる自動切替の機能の有無も、実際に停電になった際を想定して判断しましょう。
設置費用と補助金
設置費用には、本体価格と工事費用があります。補助金も本体価格に適用できるものと工事費用に適用できるものがあります。
条件を満たしているかなどを含め十分に試算してみる必要があるでしょう。
EVの充放電のタイミングを考慮する
それぞれのライフスタイルによって、車を移動させる時間帯は異なります。
例えば昼間働いている方で車通勤の方は、日中家庭で充電することができません。夕方や朝の電気代が高い時間帯にしっかり家庭に供給できるか、少し不安です。
ライフスタイルに応じてセカンドカーをEVにするなどの工夫が必要になってきます。
蓄電を十分に行えるか、放電したいタイミングにEVが家庭にあるかどうかは十分検討する必要がありそうです。
設備のメンテナンス費用や保証期間
太陽光発電システム
- 定期点検費用:約2〜5万円/回(4〜5年毎推奨)
- パワコン交換:約20〜40万円(寿命10〜15年)
- 保証:メーカーによりますが、モジュール出力保証は25年、機器保証は10〜15年が一般的
EV
- バッテリー点検:約1万円/回(1〜2年毎推奨)
- ブレーキ・タイヤ交換:ガソリン車より負担は少ないが、消耗品は交換が必要
- 保証:バッテリーは8〜10年or16万kmのメーカー保証が一般的
V2H
- 定期点検費用:約1〜3万円/回(5年毎推奨)
- 機器の寿命:約10〜15年(パワコンと同程度)
- 保証:メーカーによりますが、5〜15年の保証が一般的
まとめ:太陽光×EVは本当にお得なのか?
メリット・デメリットまとめ
メリット
- 電気代・燃料代を節約できる
- 停電時に電気を運べる
- 環境に優しい
デメリット
- 初期費用が高い
- 車で移動中は蓄電できない
お得に運用するポイント
太陽光×EVはメリットもありデメリットもある、ということをお伝えしてきました。
お得に運用するポイントをまとめてみました
- まずは現在の燃料代・電気代を知る
- 導入コストを計算する
- 導入後の燃料代・電気代をシミュレーションする
※ライフスタイルやメンテナンス費用も考慮する
導入コストが高額になるケースもありますし、必ずしも試算通りにはいかないので熟考する必要があります。お得さを重視するのであれば、長期的な投資をする目線で考えることが重要です。
結論:お得なのか
結論として、お得になるかどうかは現在の電気料金プラン・売電金額・補助金・ライフスタイルなどが影響するので必ずしもお得になるとは言い切れません。
お得になる可能性は高いと言えます。
考え方にもよるかと思いますが「投資目線のお得」だけでなく停電対策やエネルギー代高騰対策など「保険目線のお得」も大事だと思っています。
「ガソリン代が上がったらどうしよう、電気代が上がったら困る」と自分ではどうしようもできないことで一喜一憂したくはありません。
それならば自分で産生したエネルギーで生活すればいいですし、将来の備えに対してある程度お金をかけるのは必要というのが私の考えです。
そして何より!
私と同じく電気やEVが好きな方は、楽しさ重視でいきましょう!

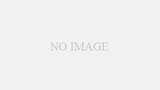
コメント